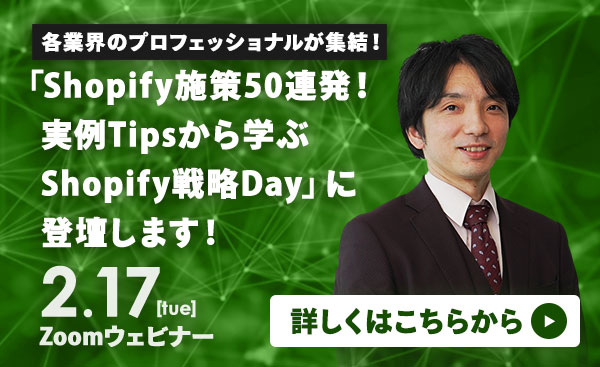【クーボンの海外リユース探訪記]】Vol.60 インド編4
お知らせコラム海外リユース探訪記2025-07-29
この連載は、世界を股にかけた循環型社会を作るために、弊社代表の大久保が見てきた海外のリユース情報や旅行記をお届けするコラムです。
最新の連載はリユース経済新聞の紙面で読むことができます。
インドはリユースが根付く可能性を秘めていると同時に、「課題のるつぼ」でもある。
急速な都市化と農村部の格差、環境汚染、児童労働、そして複雑な宗教・身分制度の共存──。
大量生産・大量消費の時代が終わりつつある今、そんなインドに「日本のリユースは貢献できるのか?」
コットン畑労働者が支払う大量生産・大量消費の代償
ラージャスターン州のコットン畑

コットン加工工場の綿の山と巨大なショベルカー
インド北西部に位置するラージャスターン州のガンガナガルは、綿花の主要生産地として知られている。
インドの綿花生産量は世界トップクラスであり、中国やアメリカと並ぶ存在だ。
中でもこのラージャスターン州は、乾燥した気候にもかかわらず灌漑農業によってコットン栽培が根付いてきた地域であり、安価な労働力と輸出志向の生産構造によって、近年注目されている。
ガンガナガルまでは、デリーから陸路で約400キロ。
約7時間車を走らせ、ようやく視界の先に真っ白な綿が揺れる畑が広がってきた。
コットンボールが実った畑は、遠目には雪が降ったように見える。
その美しさとは裏腹に、畑には重く張り詰めた空気が漂っていた。
収穫作業の真っ只中だった。労働者の大半は女性と子供達。手作業でコットンの実を摘んでいく。
炎天下のもとで、黙々と、淡々と。
「朝6時から夕方6時まで。休憩は1時間。
1日で得られる報酬は、およそ150〜200ルピー(取材時で約300〜400円)」という。
加えて、農薬や化学肥料の影響も深刻だった。
手袋もマスクもなしで作業しているため、皮膚疾患や呼吸器障害が多く、毎年何人も体調を崩して、働けなくなり村を離れる者もいるという。
有機栽培を阻むファストファッション需要
農村にあるコットン加工工場「EkakshAgro Industries」に立ち寄った。
敷地に足を踏み入れた瞬間、私は圧倒された。
綿が山のように積まれ、それを巨大なショベルカーが覆うように動いていた。
工場内には、綿と種を分離する脱穀機、圧縮梱包するプレス機が並ぶ。
これが全て、日本やヨーロッパ、バングラデシュのアパレル工場へと出荷されるのだと工場長はいう。
この綿がやがてシャツになり、ワンピースになり、
量販店やECモールで〝手頃なファッション〟として売られていく。
だが、その裏側には、化学物質で荒れた土と、黙々と働く農民の姿があった。
工場の隣にある「有機栽培エリア」も訪れたが、そこにはほとんどコットンの姿はなかった。
工場の技術責任者は、肩をすくめて言った。
化学肥料を使わず、自然の力だけで育てるには、手間と時間と土地がかかりすぎる。
インドのように水不足が深刻な地域では、通常の半分しか収穫できないオーガニックコットンは現実的でないというのだ。
だが私は、それでも諦めるべきではないと思った。
「リユース」によって新品のアパレル需要を抑えることができれば、綿花の過剰生産を抑制できる。
オーガニックの市場が育つことに頼らなくても、需要そのものを変えることができる。
これは、私たちリユース業界が目指す”サーキュラーエコノミー”の真骨頂だと、確信を深めた瞬間だった。

株式会社ワサビ
代表取締役 大久保裕史
1975年大阪府出身。リユースのキャリアは前職の小さな古着屋からスタートし、EC興隆期前にノウハウを積み重ね、楽天市場中古部門の初代ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞。2012年に株式会社ワサビを創業。現在は日本だけでなく海外 × リユース × technologyこの3つに特化した一元管理システムの開発から、日本から世界へとワールドワイドなネットワークでマーケットを拡大中。