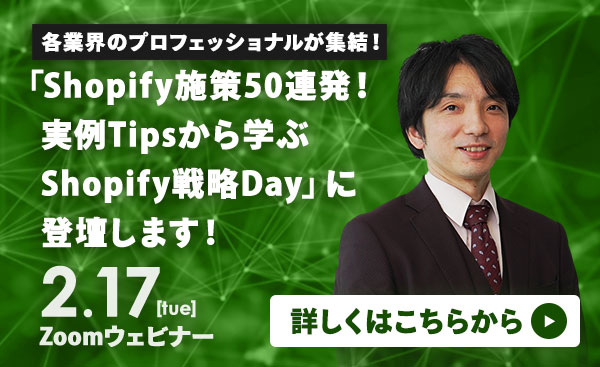【東洋経済オンラインにコメントが掲載されました】 「安全じゃない」「変な虫も一緒に届いた」などの声もあるが…批判を一蹴「SHEIN」「Temu」儲けのカラクリ
お知らせコラム2025-06-30
2025年06月30日、東洋経済オンラインに「『安全じゃない』『変な虫も一緒に届いた』などの声もあるが…批判を一蹴「SHEIN」「Temu」儲けのカラクリ」の記事が掲載されました。
弊社代表の大久保が取材を受け、コメントを寄せています。
https://toyokeizai.net/articles/-/886344
また、Yahoo!ニュースでも記事の内容が取り上げられました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/daf68febff3a6a31483d22a3b9510a101d1e3821
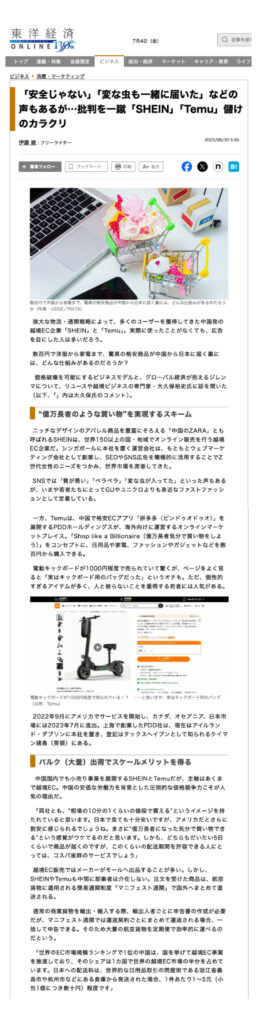
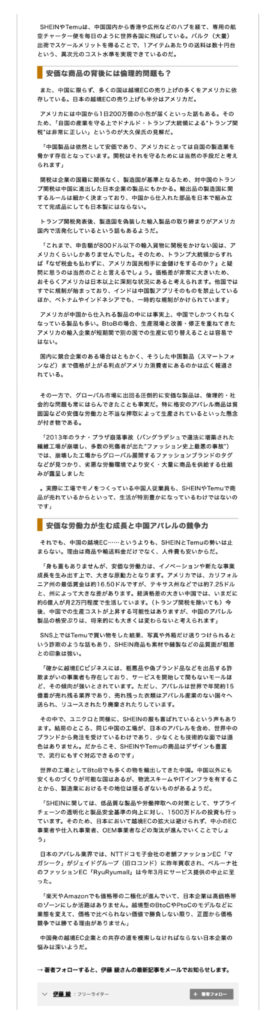
目次
「安全じゃない」「変な虫も一緒に届いた」などの声もあるが…批判を一蹴「SHEIN」「Temu」儲けのカラクリ

強大な物流・通関戦略によって、多くのユーザーを獲得してきた中国発の越境EC企業「SHEIN」と「Temu」。実際に使ったことがなくても、広告を目にした人は多いだろう。
数百円で洋服から家電まで、驚異の格安商品が中国から日本に届く裏には、どんな仕組みがあるのだろうか?
価格破壊を可能にするビジネスモデルと、グローバル経済が抱えるジレンマについて、リユースや越境ビジネスの専門家・大久保裕史氏に話を聞いた(以下、「」内は大久保氏のコメント)。
“億万長者のような買い物”を実現するスキーム
ニッチなデザインのアパレル商品を豊富にそろえる「中国のZARA」とも呼ばれるSHEINは、世界150以上の国・地域でオンライン販売を行う越境EC企業だ。シンガポールに本社を置く運営会社は、もともとウェブマーケティング会社として創業し、SEOやSNS広告を積極的に活用することでZ世代女性のニーズをつかみ、世界市場を席巻してきた。
SNSでは「質が悪い」「ペラペラ」「変な虫が入ってた」といった声もあるが、いまや若者たちにとってGUやユニクロよりも身近なファストファッションとして定着している。
一方、Temuは、中国で格安ECアプリ「拼多多(ピンドゥオドゥオ)」を展開するPDDホールディングスが、海外向けに運営するオンラインマーケットプレイス。「Shop like a Billionaire(億万長者気分で買い物をしよう)」をコンセプトに、日用品や家電、ファッションやガジェットなどを数百円から購入できる。
電動キックボードが1000円程度で売られていて驚くが、ページをよく見ると「実はキックボード用のバッグだった」というオチも。ただ、個性的すぎるアイテムが多く、人と被らないことを重視する若者には人気がある。

電動キックボードが1000円程度で売られている!?……と思いきや、実はキックボード用のバッグ
(出所:Temu)
2022年9月にアメリカでサービスを開始し、カナダ、オセアニア、日本市場には2023年7月に進出。上海で創業したPDD社は、現在はアイルランド・ダブリンに本社を置き、登記はタックスヘイブンとして知られるケイマン諸島(英領)にある。
バルク(大量)出荷でスケールメリットを得る
中国国内でも小売り事業を展開するSHEINとTemuだが、主軸はあくまで越境EC。中国の安価な労働力を背景とした圧倒的な価格競争力こそが人気の理由だ。
「両社とも、“相場の10分の1くらいの値段で買える”というイメージを持たれていると思います。日本で見ても十分安いですが、アメリカだとさらに割安に感じられるでしょうね。まさに“億万長者になった気分で買い物できる”という感覚がウケてるのだと思います。しかも、どちらもだいたい5日くらいで商品が届くのですが、このくらいの配送期間を許容できる人にとっては、コスパ抜群のサービスでしょう」
越境EC販売ではメーカーがモールへ出品することが多い。しかし、SHEINやTemuも中間に卸業者は介在しない。注文を受けた商品は、航空貨物に適用される簡易通関制度「マニフェスト通関」で国外へまとめて直送される。
通常の商業貨物を輸出・輸入する際、輸出入者ごとに申告書の作成が必要だが、マニフェスト通関では運送契約ごとにまとめて運送される場合、一括して申告できる。そのため大量の航空貨物を定期便で効率的に運べるのだという。
「世界のEC市場規模ランキングで1位の中国は、国を挙げて越境EC事業を推進しており、そのシェアは1カ国で世界の越境EC市場の半分を占めています。日本への配送料は、世界的な日用品取引の問屋街である浙江省義烏市や杭州市などにある倉庫から発送された場合、1件あたり1〜5元(小包1個につき数十円)程度です」
SHEINやTemuは、中国国内から香港や広州などのハブを経て、専用の航空チャーター便を毎日のように世界各国に飛ばしている。バルク(大量)出荷でスケールメリットを得ることで、1アイテムあたりの送料は数十円台という、異次元のコスト水準を実現できているのだ。
安価な商品の背後には倫理的問題も?
また、中国に限らず、多くの国は越境ECの売り上げの多くをアメリカに依存している。日本の越境ECの売り上げも半分はアメリカだ。
アメリカには中国から1日200万個の小包が届くといった話もある。そのため、「自国の産業を守る上でドナルド・トランプ大統領による“トランプ関税”は非常に正しい」というのが大久保氏の見解だ。
「中国製品は依然として安価であり、アメリカにとっては自国の製造業を脅かす存在となっています。関税はそれを守るためには当然の手段だと考えられます」
関税は企業の国籍に関係なく、製造国が基準となるため、対中国のトランプ関税は中国に進出した日本企業の製品にもかかる。輸出品の製造国に関するルールは細かく決まっており、中国から仕入れた部品を日本で組み立てて完成品にしても日本製にはならない。
トランプ関税発表後、製造国を偽装した輸入製品の取り締まりがアメリカ国内で活発化しているという話もあるようだ。
「これまで、申告額が800ドル以下の輸入貨物に関税をかけない国は、アメリカくらいしかありませんでした。そのため、トランプ大統領からすれば『なぜ税金も払わずに、アメリカ国民相手に金儲けをするのか?』と疑問に思うのは当然のことと言えるでしょう。価格差が非常に大きいため、おそらくアメリカは日本以上に深刻な状況にあると考えられます。他国ではすでに規制が始まっており、インドは中国製アプリそのものを禁止しているほか、ベトナムやインドネシアでも、一時的な規制がかけられています」
アメリカが中国から仕入れる製品の中には事実上、中国でしかつくれなくなっている製品も多い。BtoBの場合、生産現場と改善・修正を重ねてきたアメリカの輸入企業が短期間で別の国での生産に切り替えることは容易ではない。
国内に競合企業のある場合はともかく、そうした中国製品(スマートフォンなど)まで価格が上がる利点がアメリカ消費者にあるのかは広く報道されている。
その一方で、グローバル市場に出回る圧倒的に安価な製品は、倫理的・社会的な問題も常にはらんできたことも事実だ。特に格安のアパレル商品は貧困国などの安価な労働力と不当な搾取によって生産されているといった懸念が付き物である。
「2013年のラナ・プラザ崩落事故(バングラデシュで違法に増築された繊維工場が崩壊し、多数の死傷者が出た“ファッション史上最悪の事故”)では、崩壊した工場からグローバル展開するファッションブランドのタグなどが見つかり、劣悪な労働環境でより安く・大量に商品を供給する仕組みが露呈しました。
実際に工場でモノをつくっている中国人従業員も、SHEINやTemuで商品が売れているからといって、生活が特別豊かになっているわけではないのです」
安価な労働力が生む成長と中国アパレルの競争力
それでも、中国の越境EC……というよりも、SHEINとTemuの勢いは止まらない。理由は商品や輸送料金だけでなく、人件費も安いからだ。
「身も蓋もありませんが、安価な労働力は、イノベーションや新たな事業成長を生み出す上で、大きな原動力となります。アメリカでは、カリフォルニア州の最低賃金は約16.50ドルですが、テキサス州などでは約7.25ドルと、州によって大きな差があります。経済格差の大きい中国では、いまだに約6億人が月2万円程度で生活しています。(トランプ関税を除いても)今後、中国での生産コストが上昇する可能性はありますが、中国のアパレル製品の格安ぶりは、将来的にも大きくは変わらないと考えられます」
SNS上ではTemuで買い物をした結果、写真や外箱だけ送りつけられるという詐欺のような話もあり、SHEIN商品も素材や縫製などの品質面が粗悪との印象は強い。
「確かに越境ECビジネスには、粗悪品や偽ブランド品などを出品する詐欺まがいの事業者も存在しており、サービスを開始して間もないモールほど、その傾向が強いとされています。ただし、アパレルは世界で年間約15億着が売れ残る業界であり、売れ残った衣類はアパレル産業のない国々へ送られ、リユースされたり廃棄されたりしています。
その中で、ユニクロと同様に、SHEINの服も喜ばれているという声もあります。結局のところ、同じ中国の工場が、日本のアパレルを含め、世界中のブランドから発注を受けているわけであり、少なくとも技術的な面では遜色はありません。だからこそ、SHEINやTemuの商品はデザインも豊富で、流行にもすぐ対応できるのです」
世界の工場としてBtoBでも多くの物を輸出してきた中国。中国以外にも安くものづくりが可能な国はあるが、物流スキームやITインフラを有することから、製造業におけるその地位は揺るぎないものがあるようだ。
「SHEINに関しては、低品質な製品や労働搾取への対策として、サプライチェーンの透明化と製品安全基準の向上に対し、1500万ドルの投資も行っています。そのため、日本において越境ECの拡大は避けられず、中小のEC事業者や仕入れ事業者、OEM事業者などの淘汰が進んでいくことでしょう」
日本のアパレル業界では、NTTドコモ子会社の老舗ファッションEC「マガシーク」がジェイドグループ(旧ロコンド)に昨年買収され、ベルーナ社のファッションEC「RyuRyumall」は今年3月にサービス提供の中止に至った。
「楽天やAmazonでも価格帯の二極化が進んでいて、日本企業は高価格帯のゾーンにしか活路はありません。越境型のBtoCやPtoCのモデルなどに業態を変えて、価格で比べられない価値で勝負しない限り、正面から価格競争では勝てる理由がありません」
中国発の越境EC企業との共存の道を模索しなければならない日本企業の悩みは深いようだ。
著者:伊藤 綾(フリーライター)
コメント:大久保裕史(株式会社ワサビ代表)

株式会社ワサビ
代表取締役 大久保裕史(オオクボ・ヒロシ)
1975年大阪府出身。リユースのキャリアは前職の小さな古着屋からスタートし、EC興隆期前にノウハウを積み重ね、楽天市場中古部門の初代ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞。2012年に株式会社ワサビを創業。現在は日本だけでなく海外 × リユース × technologyこの3つに特化した一元管理システムの開発から、日本から世界へとワールドワイドなネットワークでマーケットを拡大中