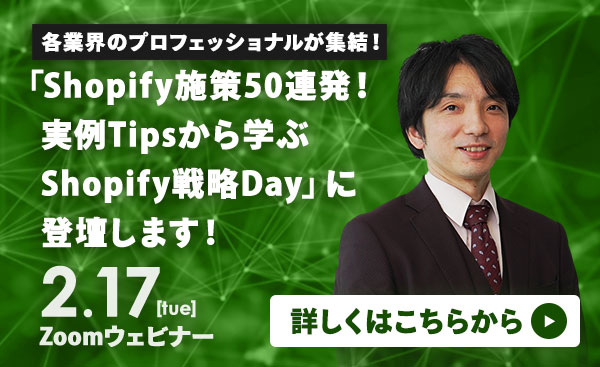リユースフェス2026開催レポート
お知らせレポート2025-10-30
この度、「リユースフェス」の取り組みを、千葉テレビ放送(チバテレ)の
ニュース情報番組「モーニングコンパス」にてご紹介いただきました!
目次
業界の未来を読み解く3つの重要セッション
2025年9月30日(火)弊社が事務局を務めるリユースフェス事務局主催のリユースフェス2026が行われました。
業界の「今」と「未来」を鋭く読み解くために構成された、主要3セッションの模様をレポートします。

リユースフェス2026公式サイト:https://wasabi-inc.biz/reusefes
リユース業界の動向


登壇者
リユース経済新聞 代表取締役社長 瀬川 淳司氏

リユースフェスの冒頭を飾ったのは、業界の「今」をマクロな視点で切り取るこのセッションです。
登壇したのは、リユース経済新聞 代表取締役社長 瀬川 淳司氏。2025年、リユース業界のこれからについて、数多くのリユースの記事を発行してきたメディアならではの視点で鋭く考察します。平成から令和の移り変わりと共に変わりゆくリユースを語る、必聴のセッションでした。
3.3兆円市場の「光」と「影」
まず示されたのは、3.3兆円規模(2024年)へと成長し、15年連続で拡大を続けるという市場の圧倒的な好調さです。物価高による節約志向や、円安を背景としたインバウンド需要の爆発的な回復が市場を力強く牽引。特にブランド品やスマートフォン市場の伸びが著しいことが報告されました。
また、業界構造の変化にも言及。かつての「買取と販売」の一体型店舗から、高騰する金相場などを背景に「買取専門店」が急増し、「売る人」と「買う人」を繋ぐ分業化が進んでいると分析しました。
しかし、瀬川氏の鋭い考察はここからが本題でした。「実はネガティブな見方もしている」と切り出し、業界が直面する「不都合な真実」を突きつけます。
それは、環境省の調査で「この1年でリユースを利用しなかった人」の割合が、調査ごとに増加しているという衝撃的な事実。市場規模が拡大している裏で、ライトユーザーや新規参入者が減少し、「リユース人口」そのものが停滞しているのではないか、というのです。
これは、現在の市場成長が一部のヘビーユーザーによって支えられており、新規顧客の開拓が進んでいない可能性を示唆しています。瀬川氏が鳴らす警鐘は明確です。業界最大の課題は「リユースの体験価値(買う・売る)の低下」にあるのではないか、と。
好調な数字の裏に潜む本質的な課題を突きつけた、まさにイベントの幕開けにふさわしいセッションとなりました。
ECモールを徹底攻略!リユース販売力を最大化する3つの鉄則




【パネリスト】
- 篠原 星氏 (イーベイ・ジャパン株式会社 ビジネスデベロップメント部 部長)
- 西谷 健祐氏 (LINEヤフー株式会社 リユース統括本部 営業本部 本部長)
- 七尾 尋尚氏 (株式会社メルカリショップス ショップスマーチャント事業部 既存顧客営業本部 部長)
- 佐々木 康正氏 (株式会社SODA (SNKRDUNK) 法人ソリューション部 部長)

続いて、リユース販売の主戦場である「ECモール」の攻略法を探るパネルディスカッションです。ECモールの第一線で活躍する専門家たちが、販売力を最大化する具体的なポイントについて熱く語り合いました。
モール攻略の鍵は「データ」「信頼」「分散」にあり
競争激化するECモールで売上を伸ばす鍵は何か。各社の戦略から見えてきたのは、全ての事業者が実践すべき「3つの鉄則」でした。
1. チャネルの拡大(販路分散)
Yahoo!オークションの「セリ」を好む層、メルカリの巨大なマーケットプレイス、SNKRDUNKの特化型コミュニティ、そしてeBayの「越境」というグローバル市場。各モールには異なる強みと顧客層が存在します。一つのモールに固執せず、複数のチャネルに挑戦することが、新たな顧客接点を生み、販売機会を最大化します。
2. データドリブンを徹底
感覚だけに頼るのではなく、各モールが提供するデータを徹底的に活用すること。eBayの販売データ閲覧ツール、メルカリのフォロワー機能、SNKRDUNKのトレンド分析など、「誰に」「何が」「いくらで」売れているのかを正確に把握し、戦略的な出品を行うことが成功への近道です。
3. オーセンティシティ(信頼性)
リユース販売、特にECにおいて「信頼性」は最も重要な要素です。eBayやSNKRDUNKが提供する「真贋鑑定」サービスはもちろん、出品者自身も商品説明を丁寧に記載し、顧客に安心感を与える取り組みが不可欠であると各氏が強調しました。
「真贋鑑定による信頼確保」や「越境販売による新顧客開拓」など、リユース市場の次の成長フェーズを感じさせる、即効性のある知見が得られる時間でした。
地方だから勝てる!ローカル集客のこれからの戦い方




【パネリスト】
- 野村 康二郎 氏 (株式会社ジモティージモスポ事業部/VP)
- 井手 総一朗 氏 (株式会社マーケットエンタープライズパートナーリレーションユニット ユニット長)
- 月岡 克 博氏 (株式会社Faber Company (ファベルカンパニー)執行役員)

「地方は不利だ」は、もう古い。リユース市場の競争が激化する今、「地方だから勝てる」ローカル集客の具体的な戦い方 を探るセッションが開催されました。
モデレーターは、自身も埼玉で地域密着型の事業を展開する株式会社リ・アンティーク 代表取締役 近藤 俊之氏。 このセッションが他と一線を画すのは、登壇する大手企業の「成功事例」 だけでなく、ともすれば隠したくなるような「失敗談」 にまで踏み込み、「明日から実践できるアクション」 を持ち帰ることに徹底的にこだわった点でしょう。
核心は「信頼」と「失敗談」にあり!地方の強みを「仕組み」化する処方箋
セッションのゴールは明確です。それは「地方の強みを”仕組み”に変える」こと。 特に印象的だったのは、各氏が口を揃えた「信頼」の重要性でした。
ジモティー 野村氏は、オフライン店舗「ジモティースポット」での実践例を紹介。 単にモノを売買する場ではなく、「なぜ売りに来たのか」という背景までヒアリングし、顧客にとって「身近な存在」になることを重視しているとのこと。 結果、「あんたに会いに来たよ」と用事がなくても立ち寄るコミュニティスペース化し、そこから生きた口コミや紹介が生まれているという話は圧巻でした。
おいくらの井手氏は、データで「信頼」の価値を証明します。 現在注力する「自治体連携」では、自治体のホームページ経由の依頼も多く、その理由は「自治体が紹介しているから信用した」という声が多数だといいます。 一方で、査定の「スピード」の遅さが致命的な機会損失につながるケースも多く、信頼構築とスピードの両立が鍵だと指摘しました。
ローカルミエルカの月岡氏は、デジタルの側面から「信頼」を解説。 Googleマップ対策(MEO)において、検索順位の重要指標である「関連性」は「口コミの内容」に大きく左右されると語りました。
このように、地方ならではの「信頼と口コミ」を、どうやって再現性のある集客戦略に落とし込むのか? 感覚論ではない、MEO対策や口コミ設計、紹介動線の具体化 に至るまで、プロたちが鋭く切り込みます。
本セッションの最大の価値は、こうした成功事例だけでなく、事業者が陥りがちな「これをやっちゃいけない」ポイント—すなわち大手企業のリアルな失敗談—まで共有された点にあるのではないでしょうか。そこから導き出される「今日からできる実践アイデア」 は、まさに即効性のある処方箋と言えます。
パネルディスカッションでは、「口コミや紹介の仕組み化」 、「MEOや検索の集客への転換」 、そして「広告コストと口コミの最適バランス」 という、事業者が今最も知りたい核心に迫りました。
綺麗事ではない、現場の泥臭い知見と具体的なアクションプラン。 ローカル集客の「これからの戦い方」 を指し示す、非常に中身の濃い時間となりました。
イベント総括:2026年リユース市場の針路

今回のリユースフェスでレポートした3つのセッションには、業界の未来を読み解く共通のキーワードが浮かび上がりました。それは「信頼の再構築」と「デジタル・データの徹底活用」です。
Session 1で示された「リユース人口の停滞」と「体験価値の低下」というマクロな課題。それに対し、Session 2(ECモール)は「真贋鑑定」や「データ活用による顧客理解」を、Session 3(ローカル集客)は「地域密着のコミュニティ化」や「MEO対策」を、それぞれの領域からの解決策として提示しました。
市場が右肩上がりの成長期から、真の価値が問われる成熟期へと向かう中、もはや小手先のテクニックだけでは生き残れません。オンラインでは「オーセンティシティ(信頼性)」を担保し、オフラインでは「身近な相談相手」としての信頼を勝ち取る。そして、それら全ての活動をデータで裏付け、最適化していくこと。
2026年のリユース市場の針路は、この「信頼」と「デジタル」の両輪をいかに力強く回していくかにかかっている。そう強く感じさせられるイベントでした。
日本のリユースを世界へ
名刺交換会
名刺交換会では、参加者の皆様により多くの交流の機会をご提供するため、「チーム対抗形式」を採用いたしました。
セッションの途中でチームのメンバーが定期的に入れ替わるローテーション方式を取り入れたことで、「普段は名刺交換の時間をなかなか持て余してしまう」というゲストの方からも、「今回は本当に多くの方と交流でき、非常に有意義な時間だった」と大変嬉しいお言葉をいただくことができました。
皆様からいただいた温かいお声を励みに、来年はさらに皆様の交流が深まるよう、よりレベルアップした企画を検討してまいります。


日本企業だけでなく、他国の同業者も集うグローバルな交流の場となりました。
国境を越えた新たな繋がりが生まれる喜びの声が多数聞かれました。
私たちは、この貴重な国際的なネットワークを足がかりに、日本のリユース技術と理念を世界へと繋げていくという大きな一歩を踏み出します。来年はさらに国際色豊かで、より実りある交流会を目指してまいります。

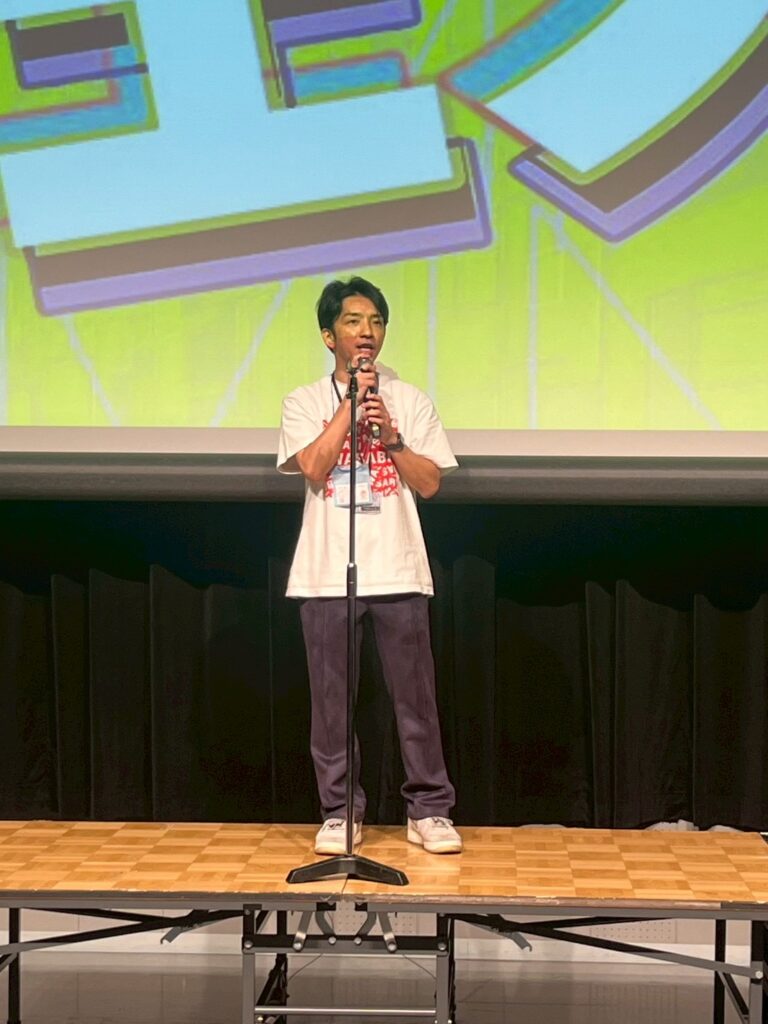
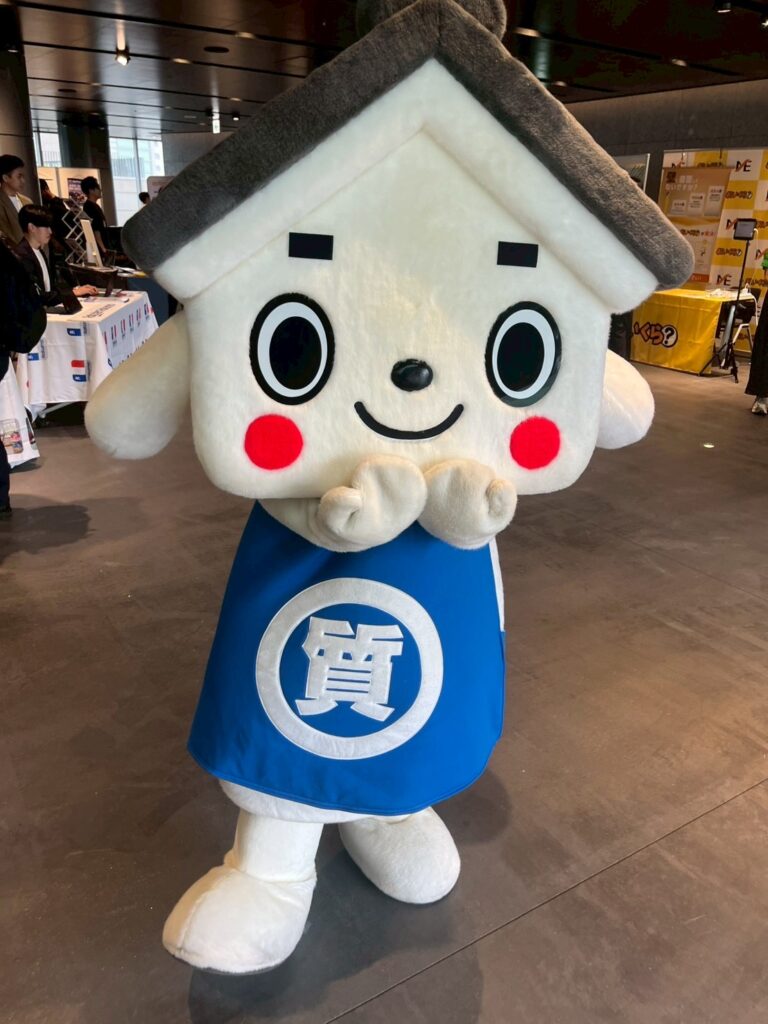



<協賛企業>






















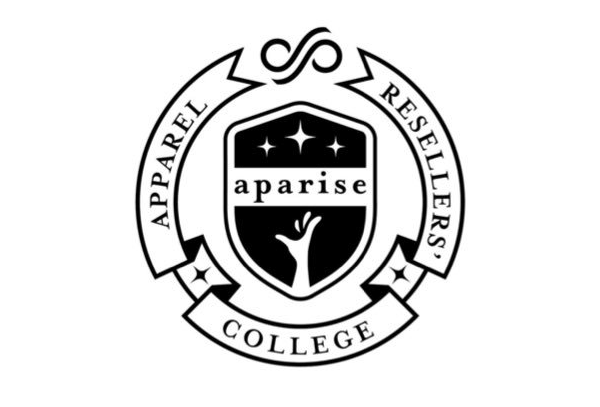











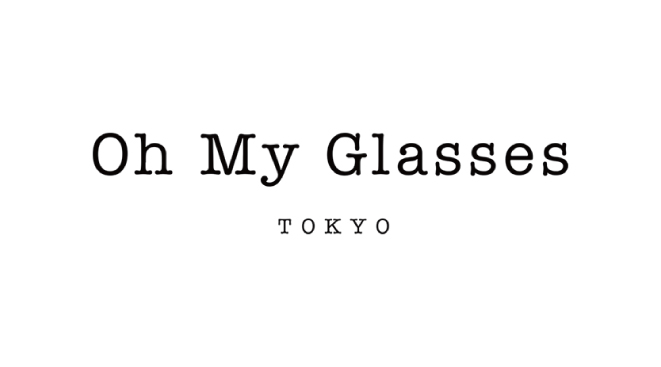

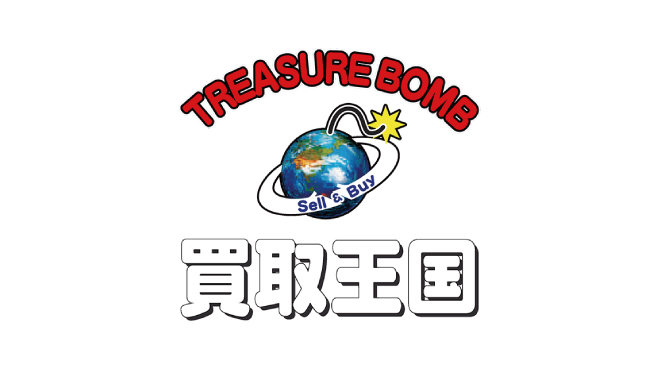





<スペシャルスポンサー>

株式会社ウリドキ様
買取マッチングサービス「ウリドキ」とリユース特化WEBメディア「ウリドキプラス」を運営。 マッチングサービスは月間30億円以上の買取依頼が発生しており、ブランド品や高級時計、ジュエリー、お酒等の高単価商材の買取が可能です。メディア掲載での問い合わせ獲得と合わせて買取店の集客アップに貢献いたします。
登壇者の皆様、協賛企業の皆様、ご参加いただいた皆様
この度はたくさんのご協力を頂き誠にありがとうございました。
リユースフェス事務局(株式会社ワサビ) スタッフ一同