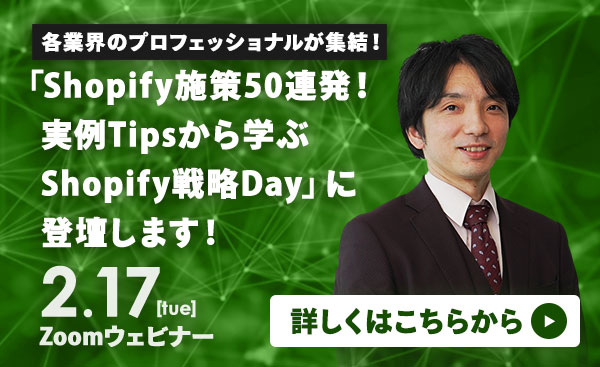【クーボンの海外リユース探訪記】Vol.57 インド編1
お知らせコラム海外リユース探訪記2025-06-12
この連載は、世界を股にかけた循環型社会を作るために、弊社代表の大久保が見てきた海外のリユース情報や旅行記をお届けするコラムです。
最新の連載はリユース経済新聞の紙面で読むことができます。
リユースは単なる「中古品の売買」ではない。商品の品質保証、真贋鑑定、整備・修理の技術、物流インフラ、そして消費者意識と文化。こうした多層的な要素が絡み合ってはじめて成り立つものだ。
技術者のキャリア形成を拡大
ギグワークの修理業者

「Prime Digitronics Services」の工房も見学させてもらった
その中でも特に難しいのが、文化と制度の壁を越えることだ。 インドには「中古=貧困層向け」という偏見も根強く残っている。また法制度も日本とは大きく異なり、中古家電の輸入は原則禁止と、リユースが根付きにくい要素が多い。
スポット勤務という
技術者の新たな働き方
インド南部に位置するカルナータカ州の州都・バンガロールは「インドのシリコンバレー」とも称され、グーグル、アマゾン、インフォシス、ウィプロといった国内外のIT企業がオフィスを構える、まさにテクノロジーの要衝だ。
「Prime Digitronics Services」はマックブックやアイフォーン、テレビ、洗濯機などの家電修理を手がける企業で、BtoBを中心に展開しながら、企業や個人からの修理依頼を広く受け付けている。特筆すべきはそのビジネスモデルだ。
なんと、常時オフィスに常駐している技術者はごくわずかで、大半は登録制の外部パートナー。案件が発生した際に、対応可能なスキルを持つ技術者がスポット対応する。
いわゆる「ギグワーカー」モデルである。Uberのドライバーのように、「修理職人」をネットワークで管理し、需要に応じて稼働させている。専門性の高い修理依頼には、その分野に長けたパートナーを、簡易なメンテナンスであれば研修済みの若手を割り当てるといった、柔軟な配置が可能になる。
「社員を抱えすぎないことで、コストも抑えられますし、品質も保てます」と創業者であるラグ・ヴェンドラ氏。彼はもともと外資系電機メーカーに勤務していた技術者で、「まだ直る製品が廃棄されていくのが耐えられなかった」と起業した。
修理に出される製品の多くは、海外ブランドの高級家電。保証期間を過ぎて部品が手に入らなくなったり、正規店での修理が困難なモデルが多い。そこに目をつけ、「信頼できる修理」を手頃な価格で提供するニーズを掘り起こしたのだ。
修理スキルの民主化で
若手のキャリア形成に可能性
技術者の”働き方”もユニークだ。登録している技術者の中には、日中は別のIT企業で勤務していたり、大学で講師をしている人もいる。
夜間や週末だけ出張し、1件あたり約500~2000ルピー(23年時点で1000~4000円)を得る。この”副収入”を子どもの進学費用や、資格取得費用に充てているという。
このモデルが成り立つ背景には、バンガロールの「教育水準の高さ」と「デジタルスキル人材の厚み」がある。
修理というと日本では”熟練の職人”を思い浮かべがちだが、ここでは「電気工学を学んだ20代エンジニア」がマニュアルを駆使して作業している。これは、今後の日本においても「修理スキルの民主化」が可能であることを示唆しているのではないだろうか。

案件が入るとギグワーカーが出勤する

株式会社ワサビ
代表取締役 大久保裕史(オオクボ・ヒロシ)
1975年大阪府出身。リユースのキャリアは前職の小さな古着屋からスタートし、EC興隆期前にノウハウを積み重ね、楽天市場中古部門の初代ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞。2012年に株式会社ワサビを創業。現在は日本だけでなく海外 × リユース × technologyこの3つに特化した一元管理システムの開発から、日本から世界へとワールドワイドなネットワークでマーケットを拡大中